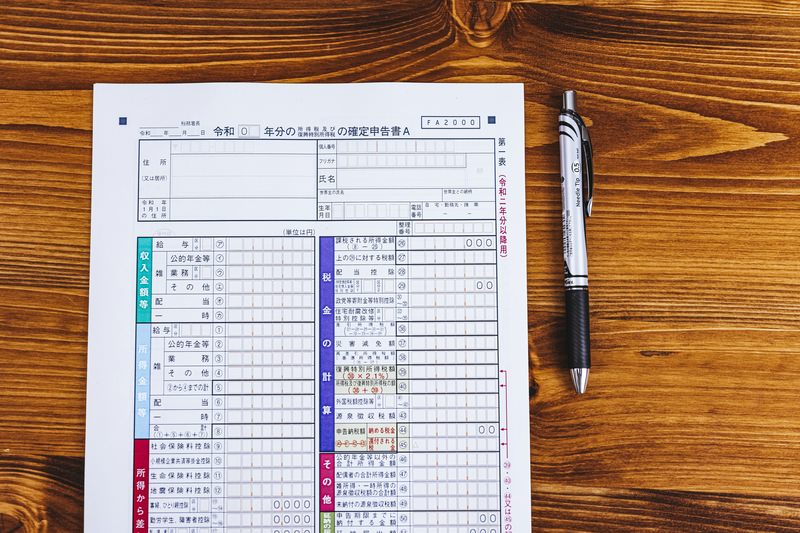国民民主党が今年10月の衆院選で掲げていた政策のうち、年収の壁を現在の103万円から178万円に上げ、手取り収入を増やそうというものがありました。選挙結果によって、国民民主党の議席を増やし、キャスティングボートを握るようになりました。そのため、与党である自民党と公明党は、国民民主党の主張について協議をすることまで至ったところです。では、そもそも年収の壁とはどういうものなのか。ファイナンシャルプランナーの目線で説明します。
そもそも年収103万円の壁とは?
家族を養うために生計が一緒の家族に対し、配偶者控除や扶養控除があります。その控除を受ける場合は、所得が0円である必要があります。例えば、父が納税者で大学生の息子は扶養親族とした場合、息子がアルバイトしたとして、収入が合っても、所得が0円であれば、扶養控除が受けられます。
所得が0円で済む限度額は、
給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=103万円
となります。
この金額を超えると、当然、大学生の息子に対して所得税が発生(大学生の場合、勤労学生控除27万円が使えるので、収入130万円までは所得税は発生しません。)するとともに、納税者は扶養控除を受けることができず、所得税の負担増になります。普通の扶養親族であれば38万円、大学生世代(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満)である特定扶養親族の扶養控除は63万円となるので、仮に税率が10%の人の場合、普通の扶養親族の場合3万8千円、特定扶養親族の場合6万3千円の負担増になります。
ちなみに、母(配偶者)が、年収103万円を超えた場合、母には当然所得税が発生しますが、父は配偶者特別控除を受けられるので、息子に比べ影響が軽減されることになります。
関連リンク 国税庁タックスアンサーより
なぜ、今、年収の壁を変えようとしているのか
ここ数年、与党は、年収を増やそうと色々な政策が打ち出されていますが、その中で、最低賃金の引き上げがあります。
東京都の最低賃金は、令和元年で1,013円に対して、令和6年10月からは1,163円と約14%上昇しています。
しかし、年収103万円の壁は数十年変わっておらず、この賃金上昇についていけていないため、息子が親の扶養控除を気にすると働くことを抑制してしまうのです。たとえば、年収が103万円に近づきそうになるとシフトに入らなくなり、雇用主が困ってしまう事例でてきます。
国民民主党が年収の壁を178万円にした根拠
国民民主党の10月の衆院選での公約のうちでは、所得税減税の項目では、
所得税を課す最低金額の引き上げ等を行い、賃金上昇に伴う名目所得の増加によってより高い所得税率が適用され、賃金上昇率以上に所得税の負担が増える「ブラケット・クリープ」に対応します。具体的には1995年からの最低賃金の上昇率1.73倍に基づき、基礎控除等の合計を103万円から178万円に引き上げます。物価上昇を踏まえ、通勤手当の所得税非課税枠を引き上げます。
とのことで、178万円としているようです。
確かに物価が上昇しているのに、基礎控除の引き上げの議論も必要になって来ていると思います。
本当に年収の壁が178万円になるのか?
単純に年収の壁を178万円にしてしまうと、所得税の税率が高い人ほど減税効果が高くなってしまう問題や全国知事会から地方財源の減少につながるので、壁を動かすなら、財政支援をしてほしいとの意見等もあるので、どこかで妥協案が出てくるのではないかと思います。
例えば、配偶者特別控除のように急激な負担増を避ける方法もあるでしょうし、どこかで金額の折り合いをつけることもあるでしょう。
税金は、国民の負担に直結するので、すぐには答えが出ない可能性があります。また、他にも年収の壁(社会保険)もあるので、今後、注目していきたいと思います。